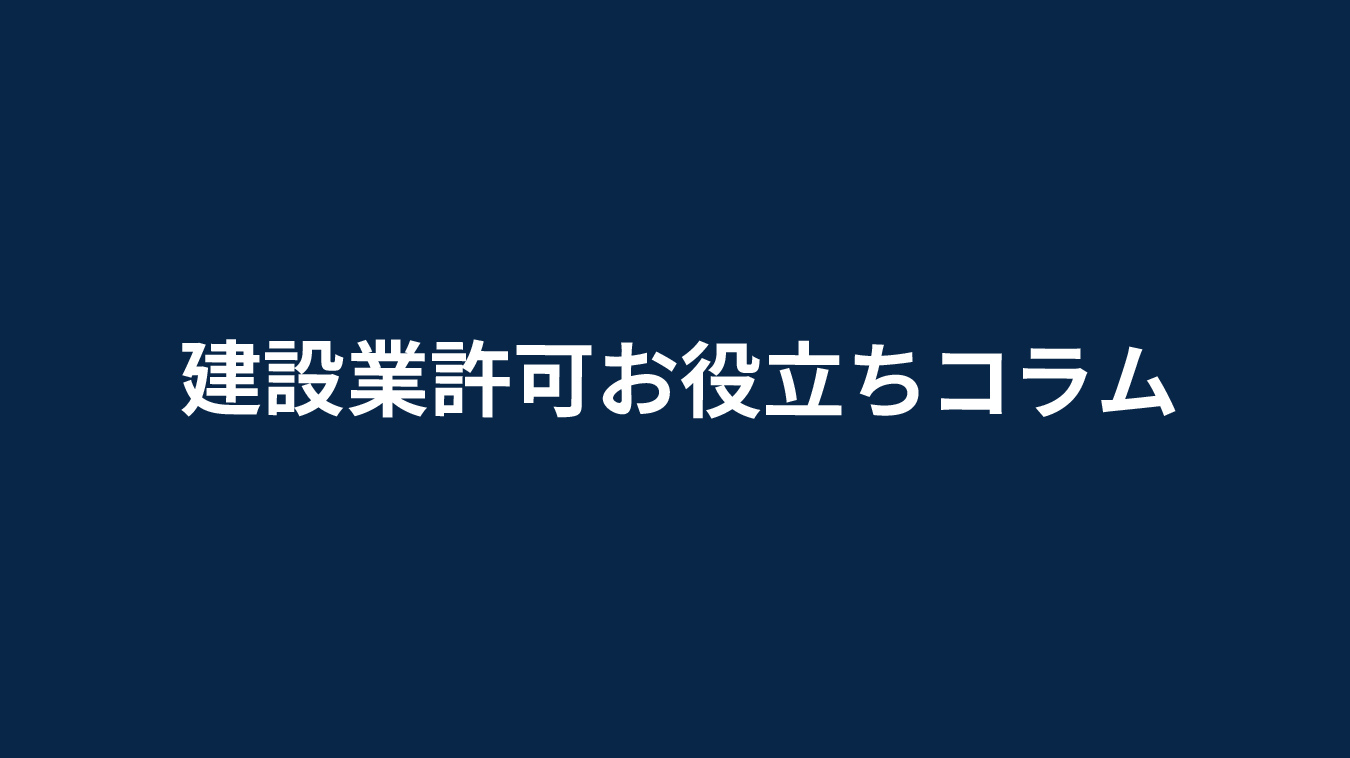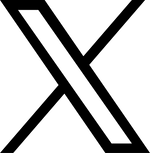建設業許可の更新は、事務所経営や業務に直結する重要な手続きです。
この記事では、自分で更新申請を行うための具体的なステップや注意点を解説します。
しかし、リソースや本業への影響を考慮すると、行政書士に依頼するメリットも大きく、その理由も説明します。
更新申請のタイミングや確認事項、必要書類についてはもちろん、行政書士への依頼を検討する際のポイントも解説します。
目次
建設業許可の更新を自分で行うためのステップ
建設業許可の更新は、事業を継続する上で欠かせない手続きです。
新規の申請より提出書類は少なくなりますが、それでも複雑な手続きには変わりありません。
ただ、専門家に依頼せずに自分で手続きをすることももちろん可能です。
以下に、自分で更新を行うためのステップを具体的に説明します。
スケジュールを把握しよう。更新申請のタイミングについて
まず、そもそも更新はいつしないといけないのかを把握してスケジュールを立てる必要があります。
建設業許可の有効期間は許可日から5年間となります。
許可日については許可取得の際に交付される「許可通知書」などで確認することができます。
許可通知書が手元にない場合は国土交通省の建設業者検索システムからも確認可能です。
建設業許可更新手続きは有効期間満了の日の3か月前から提出することができます。
注意点として、受付は更新許可申請は有効期間満了の日の30日前までに済ませておく必要があります。
必要書類一覧と準備方法
スケジュールが決まったら必要な書類を揃えます。
更新申請の書類は、新規許可申請の時より量は減りますが、それでも多くの書類が必要となりますので余裕を持って準備を進めましょう。
自分で書類集めから作成までをする場合は2ヶ月ほどはみておきたいところです。
本業の忙しい時期と被る場合はさらに余裕をみて前倒しして取り掛かることをお勧めします。
書類の記載方法などは各都道府県が作成してくれている手引きに記載があります。
記載方法などが異なっていると訂正でその分時間がかかりますので、
書類作成を進める際は必ず手引きを確認しましょう。
また、各都道府県によっては必要書類が異なる可能性もあるため、管轄の役所に相談することも可能ですので、不明点は相談しましょう。
必要な書類は以下の通りです。
新規許可申請の際の必要書類と同様の内容もありますが、更新専用の書類などもあるので注意が必要です。
新規許可申請よりは比較的少なめです。
閲覧用
- 表紙
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表(法人のみ)
- 営業所一覧表(更新用)
- 専任技術者一覧表
- 欠格要件に該当しないことの誓約書
- 健康保険等の加入状況
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・営業所長等)の一覧表
- 定款(変更があるときのみ)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体(変更があるときのみ)
- 主要取引金融機関名(変更があるときのみ)
非閲覧用
- 表紙
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書or常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書のどちらか
- 常勤役員等の略歴書-第7号 別紙(上記の前者の場合)
- 常勤役員等の略歴書-第7号 別紙1(上記の後者の場合)
- 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書-第7号 別紙2(上記の後者の場合)
- 許可申請者(法人の役員等・本人等)の住所、生年月日等に関する調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店所長等)の調書(該当者がいるとき)
- 株主(出資者)調書(変更があるとき)
- 商業登記に係る登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る)(変更があるとき)
- 「登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 身分証明書(本籍地の役場で取得)
- 健康保険及び厚生年金保険分「領収書又は納入証明書」の写し
- 雇用保険分「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え+「領収書」の写し+事業所 非該当承認通知書の写し(承認申請をしている場合)
確認資料
- 社会保険の確認資料(常勤役員等、常勤役員等を直接に補佐する者、専任技術者の常勤性確認のため)
管轄の役所に申請
各書類に正確な内容を記載し、作成が完了したら管轄の役所に申請を出します。
不備があれば指摘されますので、修正が必要です。
書類に問題がなければ、約1ヶ月ほどで許可証が交付され、更新手続きが完了します。
なお、更新手続きには手数料(基本的には5万円)がかかりますので、費用の準備をしておきましょう。
費用については下記記事で詳細を解説しています。
建設業許可の更新費用まとめ!手数料と行政書士報酬の目安も解説
建設業許可の更新を自分でする場合の注意点
更新を怠ってしまうと事業に大きな影響がある
- 新規で許可申請をやり直す必要がある
- 500万円以上の工事を請け負うことができない
- 許可番号が変わってしまう。
などのデメリットが多いため許可業者として継続して事業を行うのであれば、更新を怠るのは死活問題となります。
ですので更新はスケジュール管理から徹底して準備しておく必要があります。
リソースをたくさん使ってしまう
専門家である行政書士への報酬を抑えることができるというメリットはありますが、自分で手続きをするとなるとかなりの労力を使います。
手引きは用意されていますが読み込む量も多く時間がかかります。
不備が発生したりすると想定以上に時間や手間がかかってくるので、本業にも影響が出てしまう可能性もありますので注意が必要です。
複数業種での許可がある場合は許可有効期限をまとめておくこと
例えば
とび・土木・コンクリート工事の許可有効期限が2030年10月1日
左官工事の許可有効期限が2030年11月1日
の場合、2030年10月1日にまとめて更新をするのが良いでしょう。
許可期限がバラバラしているとその分スケジュール管理が大変です。
ですので許可期限をまとめておくことで管理しやすくなります。
更新のスケジュールを管理して把握しておくこと
自社内でスケジュールを管理しておくことが重要となります。
許可期限はいつなのか。いつ頃から準備を進めれば良いのか。必要書類はどのように取得するのか。
などを把握して予定を立てておく必要があります。
ただし、リソースの問題や専門的な知識も必要になってきます。
これらを考えるとアウトソーシングした方が合理的な場合もあると思います。
そんな時は建設業許可の専門家である行政書士にスケジュール管理から手続きまでを依頼することをおすすめします。
変更届は常に提出しておくこと
決算変更届や経営業務の管理責任者の変更などがあった際に、変更届が法定期限内に提出されていない場合は更新ができませんので注意が必要です。
変更届の提出を怠ると罰則もあるため変更があった都度提出しておく必要があります。
また、更新時に経営業務の管理責任者や専任技術者の変更がある場合は、 変更が完了した状態で更新申請をする必要があります。
行政書士への依頼を考慮する場合
前述のように更新を忘れてしまうリスクは事業に大きな影響を与えてしまうため、防ぎたいところです。
そんな時は専門家である行政書士への依頼を検討しましょう。
行政書士に任せる理由と長所
行政書士に建設業許可申請を任せる理由と長所は以下の通りです。
- 法令や手続きに精通しているためスムーズな申請が可能。
- 書類作成や手続きにかかる時間を節約でき、自分の業務に専念できる。
- 行政書士が申請手続き全体をサポートしてくれるため、安心して申請が進められる。
- スケジュールを管理してくれる
- 専門家による的確なアドバイスや対応が受けられる。
- 複雑な手続きや変更事項の対応なども対応してくれる。
料金と報酬: 費用対効果を検討
建設業の許可申請や更新手続きにおいて、専門家の支援を利用する際には、料金と報酬の費用対効果を検討することが重要です。
各専門家のサービス内容や報酬体系には差がありますので、自分の経営状況や業務内容に適した支援を選ぶためにも、十分な比較検討が必要です。
事前に費用やサービスについて説明を受け、予算に合った選択を行いましょう。
また、無料相談などを実施しているケースも多いため、利用して専門家の対応力や人間性を確認することも大切です。
自分で建設業許可更新を成功させるポイントまとめ
建設業許可の更新を自分で成功させるためには、まずはスケジュールを立てて手続きの流れを把握することが重要です。
また、費用対効果を考慮してアウトソーシングした方が良い場合は専門家の選定や、無料相談を活用して手続き方法の確認や専門家の対応力をチェックすることも有益です。
そして、手続きが完了した後も、業務内容の変更や役員の変更など、建設業許可に関連する事項に注意を払って適切な管理を行いましょう。
今回の内容を参考にして、ぜひ自分で建設業許可の更新を成功させてください。